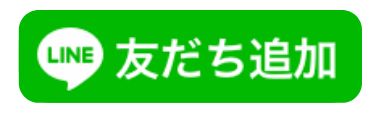今年6月、うみがめこと、私は9年ぶりにホンジュラスの地を踏むことができた。
訪問を予定していた2020年は、その年の冒頭からCovid-19に対する未知との闘い(今振り返ると「世界的大騒動」)が始まり、2023年5月に渡航規制が解かれるまで続いたことと、西アフリカにおける自身の業務との兼ね合いから、2015年を最後に、アムダマインズの活動地のうち、最も遠方に位置するホンジュラスを訪問する機会はなかなか巡ってこなかった。

AMDAはグループとして、同国を襲ったハリケーン・ミッチの被災者に対する緊急医療支援を機に、1998年から途切れることなく活動を続けてきた。主に、ニカラグアとの国境沿いに位置するエルパライソ県の丘陵地域における母子保健、家庭菜園を通じた栄養強化の他、教育や環境分野の活動、また、首都テグシガルパの都市部貧困地域における青少年育成や治安改善などの分野で、現地行政、協力団体、受益者、現地職員などとの信頼関係を軸に魅力的な事業を展開し、数多くの成果を上げてきた。
私は今回、(時計の針を戻すかの如く)古くは10年前に遡って、すでに終了した事業の「事後」もしくは「現状」確認を行うことを目的に、(時間的制約があったため)主にエルパライソ県の事業地を訪問した。概ね、当時の活動や成果は現地の直接受益者に引き継がれ、現在も最終受益者への便益が継続していることを確認することができた。直接受益者とは、プロジェクトが直接働きかける対象群の人々であり、例えば、保健行政下の職員や保健医療スタッフ、そして保健ボランティアなどがそれにあたる。他方、最終受益者とは、直接受益者が提供するサービス(診療行為や母子保健に係る助言など)を受ける側の人たちである。例えば、健診を必要とする妊婦であったり、予防接種を受ける乳幼児であったりする。
ホンジュラスに限らず、開発途上国の地域行政は手元の資源(資金や人材等)が不足しており、技術的、物質的な側面から後押しして、最大の効果をもたらすことができた時はNGO冥利に尽きると言って良い。
今回の訪ホで、特に注目をしたのは、妊婦健診を強化するために導入した超音波診断装置のその後である。10年前は、同国の公立病院に数台程度しかなく、地方の病院には皆無だったと記憶している。エルパライソ県にその後5台の超音波診断装置が導入された。
この取り組みを主導して下さったのは神奈川県にある相模原橋本ロータリークラブ(RC)である。事前調査後、米国の本部へ補助金を申請、複数のロータリアンが遠距離移動の労を惜しまず、ホ国の現場へ何度も足を運ばれ、最後まで協力を継続下さった。他方、アムダマインズは相模原橋本RCの現地側パートナーであるダンリRCとともに、協力団体として主に(直接受益者である)医療従事者を対象とした研修や、妊婦健診の重要性と診断装置の存在を最終受益者へ周知する活動などに携わった。ロータリーとアムダマインズの協力により、妊婦健診の精度が格段に上がり、多くの妊婦の方のリスクを減らし、少なくない命を救うことができた好事例である。特筆すべきは、現在これらの診断装置は子宮頸がん検診にも活用されており、2倍の効果が生じていることである。

もちろん、女性の命を守る活動であるからすべての物事がスムーズに行くわけではない。公立の医療施設への導入にあたっては、懸念すべき点も少なくなかった。
まず、持続性(長期的にサービスが提供されるかどうかの)の問題である。そして次に、すでに私営のクリニックなどですでに導入されていた場合、競合関係に陥らないか、という点である。少し事情を複雑化させるのは、公立病院などで働く医療従事者が私営のクリニックでアルバイトをしているケースである。こうした状況は医療従事者(公務員)の給与体系が十分でない途上国では一般的なことであるが、慈善団体やNGOによる介入が、ある意味において地域医療の既存の生態系を侵食する可能性があり、協力を拒む理由がないわけではない。
結論として、5台のうち3台が稼働中、1台は大病院で耐用年数を超えて大往生(その後は新しい機器を活用してサービスを提供中)、来院者から少額の検査費用を徴収し、消耗品やメンテナンスなどの費用に充てていて、サステイナビリティが確保されている。他方、最後の1台は天井裏に巣食ったコウモリのふんを避けるため、一時的に活用停止に近い状態となっており、5戦4勝1引き分けである。これはマジックと言っても過言ではない成果である。
さて、誌面が限られており、残念ながらこの原稿はここで終止符を打たせて頂く。この内容の続きについて、またそれ以外の話題については、後日当団体のホームページをご覧頂きたい。
※ニュースレター2024年秋号に掲載された記事を転載しています。
![]()
理事長
大学卒業後、民間企業に就職。その後国連ボランティアとしてカンボジアや南アフリカの業務に従事、様々なフィールド経験を通じて国際協力業界へのキャリアチェンジを決意。大学院で国際開発学を学び、ミャンマーにおける人間開発プロジェクトに従事した後、1999年、AMDAグループ入職。ベネズエラ、インドへの緊急救援チームを率いた他、ネパール、アンゴラ、インドネシアなどで様々な事業運営に携わる。2002年、AMDA海外事業本部長就任。2007年、AMDA社会開発機構設立。理事長就任。趣味は旅行、山羊肉料理の堪能。岡山のお気に入りスポットは表町商店街とオランダ通り。神奈川県出身。

世界のことをもっと知りたい!
世界の貧困地域で暮らす人々の問題と、その解決に向けた私たちの取り組みをSNSとメールマガジンでも発信しています。まずは「関心をもつ」「知る」から始めてみませんか?!(過去のメールマガジンはこちらからご覧いただけます。)