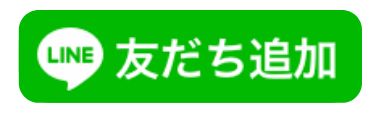うみがめ、ついにインドへ上陸 ~ 第3章「顧客サービスについて②」
第3章「顧客サービスについて①」はこちらから
前号において、インド滞在中のうみがめこと私は、限られた日数ではあったが、様々な場面において安価、安心、安全、快適な顧客サービスを提供され、時代錯誤的な先入観が覆されたことをお伝えした。そしてそれはラムチョップの一皿に凝縮されているとも述べた。蛇足的ではあるが、今回はそのことについてお伝えしたい。
ハワイ語でアオウミガメを意味し、海の守り神として尊ばれる「ホヌ」の塗装が鮮やかなハワイ行きの機体を横目に、成田空港からインドへ向かうANA便がデリーに到着した時、空は暗くなりかけていた。幸いにも、数少ない国の旅券保持者のみに与えられているアライバルビザ(Visa on Arrival)の権利を行使し、通関を素早く抜け、ホテルに到着した初日の晩は、受付で館内のレストランを紹介されたが、疲労していてそのままベッドに倒れ込んだ。
翌夕、私は紹介されたレストランに出向いた。普段は「孤独のグルメ」の如く現地のローカルレストランでB級グルメを堪能するうみがめではあるが、時にホテルのレストランに出向くこともある。ただ、コスパへの懸念が残る結果となるのが多いことも事実である。

さて、うみがめはレストランスタッフに案内され窓際の席に着いた。レストラン内のテーブルには空きが多く、客数は少なかった。もはや期待はせず、メニューの中にあったサラダと、ポップに「おすすめ」と記されていたラムチョップを迷わず注文した。まずまずのサラダを食べ終え、その後丁寧にグリルされたラム肉の攻略に取り掛かった。最初の一撃で「うーん、美味い!」井之頭五郎さんではないが、骨部をしっかりと握り、程良く弾力のあるラム肉を噛みしめ、タレ汁の風味と脂身が溶け合った絶妙の美味に舌鼓を打った。
しばらくするとシェフがスタッフとともにテーブルにやってきて、「料理はどうか?」と尋ねてきたので「素晴らしい!」と回答した。何往復か言葉を交わすうち、シェフは海外で修行を積んだネパール人だということが判った。ホテルのレストランとは言え、一人客にも関わらず、テーブルまで足を延ばすシェフはそういないだろう。恐らく、タレ汁に漬け込んでいた時間や食材の産地などについて会話を重ねたと思うが、少しアルコールが入っていたせいか、今となっては会話の詳細をよく覚えていないが、彼らの写真を撮らせていただいた。

果たして、フロントでレストランを紹介されなかったら、「おすすめ」のポップがなかったら、私は極上のラムチョップにたどりつけただろうか。良いサービスには布石がある。感激したので、食後のデザートとコーヒーも注文し、客単価は跳ね上がった。うみがめはシェフとスタッフにうまく乗せられたのかも知れない。しかしこれが増益と経済成長につながるサービス(=付加価値向上)の基本セオリーではないか。インドは全方位、全階層で付加価値の創造にまい進中である。

最後に、日本とインドにおける顧客サービスの大きな違いを述べたい。
日本では、組織の一人ひとりが良い接客をすることが、組織全体の評価の向上につながるという理解の下、職員は一致協力して、付加価値の平均値を上げようとする。他方、インドでは(私の限られた経験から)顧客サービスのクオリティは個人ごとに異なるという前提があり、組織的な評価よりも、職員個々人の評価が重要視されているように感じた。従って、ホテルなどでは、長距離バスのチケット手配から誕生日ケーキの差し入れまで、上司の命によるものではなく、個人の発案としてサービスが提供されることが多いようだ。そしてチェックアウトの際、Googleやホテルアプリの評価に自身の名前を書き込んで欲しい、と懇願されることが何度かあった。
これはデリーだけでなく、その後訪問したインド北東部でも同様の場面に遭遇した。もしかしたら、経営陣による職員の評価がそうした口コミ投稿に基づいて行われている可能性があり、またそれが給与や賞与に反映されている可能性もあり拙速な判断は禁物だが、集団主義か個人主義か、もちろん一括りにはできないものの、そのような言葉で日本とインドの顧客サービスの違いの一端を示すことが可能かも知れない(七不思議7)。
理事長
大学卒業後、民間企業に就職。その後国連ボランティアとしてカンボジアや南アフリカの業務に従事、様々なフィールド経験を通じて国際協力業界へのキャリアチェンジを決意。大学院で国際開発学を学び、ミャンマーにおける人間開発プロジェクトに従事した後、1999年、AMDAグループ入職。ベネズエラ、インドへの緊急救援チームを率いた他、ネパール、アンゴラ、インドネシアなどで様々な事業運営に携わる。2002年、AMDA海外事業本部長就任。2007年、AMDA社会開発機構設立。理事長就任。趣味は旅行、山羊肉料理の堪能。岡山のお気に入りスポットは表町商店街とオランダ通り。神奈川県出身。

世界のことをもっと知りたい!
世界の貧困地域で暮らす人々の問題と、その解決に向けた私たちの取り組みをSNSとメールマガジンでも発信しています。まずは「関心をもつ」「知る」から始めてみませんか?!(過去のメールマガジンはこちらからご覧いただけます。)