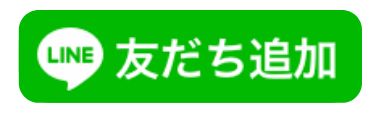うみがめ便り~20年の時を超えて、オノリンブの浜で思う①
前号の便りまでは、数回にわたりインドに対して抱いた関心、インドにおける体験と感想などを書かせて頂いた。インドを再訪した理由は、2001年の1月に同国グジャラート近郊で発生した大地震の被災地における医療救援活動の記憶をたどったことである。加えて、東南アジアを訪問するたびに触れたインド文化とその伝播の歴史への関心がきっかけだった。
同様に、インドネシアのニアス島(スマトラ島北部沖)への再訪も、その根をたどると2004年と2005年に発生した大地震であった。今回から3度にわたり、ニアス島における過去及び現在の出来事を書かせて頂きたい。

吾輩はうみがめである。熱帯地域に長く滞在していると季節は雨期と乾期に大別されるが、一年を通して気温がほぼ安定していることから衣替えも必要なく、季節はゆっくり平坦に進んでいるかのように感じる。他方、日本に滞在していると変化の度合いと速度に驚くことがよくある。春夏秋冬に梅雨や台風の季節を加えると、寒暖の差が大きく、季節々々の色彩が豊かである反面、目まぐるしい。桜の季節は2週間で終わる。一か所に立ち止まっていたら、季節が自身の周囲をぐるぐると駆けていくかのようだ。日本に住むと時が早く進む(≒早く歳をとる)ので、神様は日本人に長生きという贈り物をしたのではないだろうか。
竜宮城と比較し、人間界では何倍もの速さで時が経過するため、うみがめの年齢を人間のそれに換算すると、私はすでに高齢期の入り口に足を踏み入れており、陸の上において残された時間はあまり多くない。玉手箱を開けた浦島太郎が一瞬にして数百年の時を失った悲劇は、この点に依拠する。ゆっくり泳ぎ、ゆっくり歩くことを信条としてきたが、身体の状況を加味して逆算すると余裕がないことに気づき、これからは足早に世界の海を巡ることにした。
昨年11月から今年3月までの間は、業務によって傷ついた心身をいたわりながら、インドからインド洋をゆっくり東へ移動し、インドネシアのニアス島にたどり着いた。海底から温泉が湧き出ていたオノリンブ(Onolimbu)の浜辺だ。白い砂浜の先にはサンゴが育ち、大小の熱帯魚が舞っていた。竜宮城への入り口からそう遠くない浜辺である。
ニアス島は、スマトラ島の西海岸の沖合約100キロの場所に位置する人口約80万人、面積約5千平方キロの小島である。スマトラ島側にはシボルガという比較的大きな港町があり、ニアス島との間を12~13時間かけて、フェリーがほぼ毎日行き来している。ただし、当時は波が高いと沈没の恐れもある不確実性の高いフェリーだった。他方スマトラ島北部の大都市メダンからは、小型のジェット機(約2時間のフライト)で来島することも可能である。2005年当時はハリボテ同様のプロペラ機だったと記憶している。低空飛行だったので下界が良く見えた。途中、スマトラ島の中央部に差し掛かると、世界最大のカルデラ湖であるトバ湖を眼下に見ることができ、そのほとりに立つ白色のキリスト像をはっきり眺めることもできた。
先ほどニアスを小島と書いたが、日本全体の約1.3倍の面積を有するスマトラ島が巨大であるため、そのような記載になったが、佐渡島の約2.7倍の面積を有し、千葉県に匹敵する。人口は鳥取県や島根県をしのぐ。したがって決して小さくはない。島の南側と西側は海底の地形、その起伏に起因した波の高さが売りで、サーファーの聖地とも呼ばれ、過去世界大会なども開催されたことがある。
さらに歴史を遡ると、つい最近まで、島の一部地域には人肉食の習慣(カニバリズム)があったと言われ、当初、島民の凶暴性の背景が語られていた。もっとも、雇用した現地スタッフや地域の住民を含め、大概の人々は非常に温和で、凶暴という言葉の対極にあると感じた。ニアス島と私の最初の交差点は20年前、そして2025年3月、とても短かったが2度目の交差点を迎えた。
当時(AMDA社会開発機構設立前)のAMDAは、巨大地震による深刻な被災状況に鑑み、やや性質の異なる大規模な支援活動をスマトラ島の最北端に位置するアチェとニアス島の二か所において展開した(地図を参照)。

そして当時、海外事業本部長だった私は、カンボジアやミャンマーにおける大型案件の最終局面を離れ、2005年9月、直接のパートナーとなったUNHCRとの契約を機に、ニアス島へ向かうことになった。(続く)
理事長
大学卒業後、民間企業に就職。その後国連ボランティアとしてカンボジアや南アフリカの業務に従事、様々なフィールド経験を通じて国際協力業界へのキャリアチェンジを決意。大学院で国際開発学を学び、ミャンマーにおける人間開発プロジェクトに従事した後、1999年、AMDAグループ入職。ベネズエラ、インドへの緊急救援チームを率いた他、ネパール、アンゴラ、インドネシアなどで様々な事業運営に携わる。2002年、AMDA海外事業本部長就任。2007年、AMDA社会開発機構設立。理事長就任。趣味は旅行、山羊肉料理の堪能。岡山のお気に入りスポットは表町商店街とオランダ通り。神奈川県出身。

世界のことをもっと知りたい!
世界の貧困地域で暮らす人々の問題と、その解決に向けた私たちの取り組みをSNSとメールマガジンでも発信しています。まずは「関心をもつ」「知る」から始めてみませんか?!(過去のメールマガジンはこちらからご覧いただけます。)