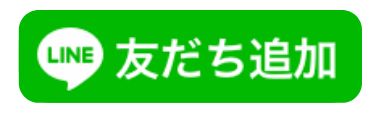うみがめ、ついにインドへ上陸 ~第1章「3つの理由②」
(前回のブログ、第1章「3つの理由①」はこちらから)
私は社会人になった後の10年間、上座部仏教の国、特にタイ、カンボジア、ミャンマーにおける業務や滞在が長かった。しかしそのどの国を訪れても、インドの神々が信奉されている光景を目のあたりにした。そして仏教寺院、仏教遺跡とされる場所にさえ、そうした神々が祭られていることに少なからず疑問を感じていた。インドの一部の人々の間では、仏教はヒンドゥー教の一派、あるいは一部であるとの解釈もあり、実際、お釈迦様であるゴータマ・シッダールタを、ビシュヌ神の化身の一つと見なす考え方もある。

アンコール・ワット 
アンコール遺跡の彫刻
しかしである。例えば、カンボジアのアンコール・ワットは、12世紀にクメール王だったスーリヤヴァルマン2世の命により建設されたことになっているが、仏教の国カンボジアにあるアンコール・ワットに、インドの神々が崇める様式で見られることをどのように解釈すれば良いのだろうか。当時のクメール王国ではヒンドゥー教が一般的に信仰されていたことの証明なのだろうか。アンコール・ワットを訪れ、ふとそんな違和感を覚えた方も少なくないだろう。
アンコール・ワットがあるシェムリアップは、トンレサップという大きな湖の北端に位置するが、下流はメコンデルタと呼ばれ、現在のベトナム南部にあたる。歴史を遡ると、ベトナム中部から南部は2世紀以降、チャム族の国、チャンパ王国の勢力下にあった。
クメール王国は成立後、常に隣国との紛争を繰り返し、一時はチャンパ王国の首都ヴィジャヤを陥落させたとも伝えられている。反対に、チャム族がトンレサップを遡ってクメール王国に攻め込むこともあったようだ。アンコール・ワットの回廊には、侵攻するチャム族を撃退する勇猛なクメール兵士の姿がレリーフとして描かれている。

ただ、チャンパ王国の隆盛期はクメール王国のそれよりも古い。ベトナム戦争時の爆撃を免れた極めて少ないミーソンの遺跡等には、アンコール遺跡に相似するようなインドの神々が彫られており、その一部は修復を経てダナン市の博物館に納められ、今はほぼ歴史から消えてしまった当時のチャム族の文化を紹介している。

つまり、2世紀頃から12世紀頃までの間、現在の東南アジア地域は、インド文化、インド宗教の強い影響を受けていたことが窺え、インド式の建築様式や神々の崇拝文化は同地域に共通したものだったのではないかと想像できる。さらに、チャム族は海洋民族でもあったことから、マレー半島からインドネシアにまたがる広大な地域における交易も盛んに行われ、その過程で、建築技術やインド文化の伝承の担い手になっていたのではないかと想像できる。
しかし、その後弱体化したチャンパ王国は18世紀に滅亡し、チャム族もヒンドゥー教からイスラム教に改宗したり、カンボジアや欧米に移住したりして、それぞれでコミュニティを形成している。現代に生きるチャム族の人は、かつて使用されていたチャム語を理解することができないため、遺跡等に彫られた文字の多くが十分に解明されないままだと言う。残念ではあるが、謎に包まれたチャンパ王国とインド文化伝承の史実を紐解くことはとても興味深く、このことがインド再訪に向けて私の背中を押した理由の一つとなった。
なお、余談が多く申し訳ないが、東南アジアの国々を持ち出さなくても、日本においてもインドの神々がしっかり根付いており、大黒天、毘沙門天、弁財天、吉祥天などが良い例である。
このような、歴史への関心は、インドに赴く大きな理由(第二の理由)となった。(続く)
![]()
理事長
大学卒業後、民間企業に就職。その後国連ボランティアとしてカンボジアや南アフリカの業務に従事、様々なフィールド経験を通じて国際協力業界へのキャリアチェンジを決意。大学院で国際開発学を学び、ミャンマーにおける人間開発プロジェクトに従事した後、1999年、AMDAグループ入職。ベネズエラ、インドへの緊急救援チームを率いた他、ネパール、アンゴラ、インドネシアなどで様々な事業運営に携わる。2002年、AMDA海外事業本部長就任。2007年、AMDA社会開発機構設立。理事長就任。趣味は旅行、山羊肉料理の堪能。岡山のお気に入りスポットは表町商店街とオランダ通り。神奈川県出身。

世界のことをもっと知りたい!
世界の貧困地域で暮らす人々の問題と、その解決に向けた私たちの取り組みをSNSとメールマガジンでも発信しています。まずは「関心をもつ」「知る」から始めてみませんか?!(過去のメールマガジンはこちらからご覧いただけます。)