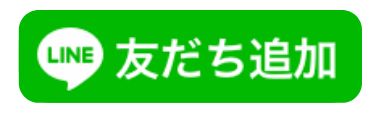うみがめ、ついにインドへ上陸 ~ 第3章「顧客サービスについて①」
第2章「インドは混沌、ではなかった」はこちらから。
うみがめは普段ゆったり、ゆっくり泳ぎ、のんびり食事を摂る。人種、否、亀種によって餌の種類は異なるが、吾輩は雑食である。若い時には肉類や魚類を好んだが、現在は野菜(うみがめ的には海藻)の摂取、バランスのとれた食事に極力重きを置いている。とは言え、肉類や魚類も捨て難い。30代の後半からは海外における生活が主となり、それまで日本ではなじみのなかったヤギ(Goat)やラム(Lamb)を好むようになった。その理由はまた別の機会に譲るとして、この度のインドでも特上のラムチョップに出会えた。

日本でも、近年ラム肉やジビエ肉がヘルシー(高たんぱく、低カロリー、低糖質)な食材として好評を得ているが、特有の臭みには好き嫌いがあるようだ。うみがめこと私は、どちらかというと臭みのない高価な北海道のラムよりも、やや癖のある輸入肉、あるいは海外で味わうラムを好む。インドのホテルで頂いたラムチョップは素材も味付けも本当に素晴らしかった。
さて、ここからが本題である。
海外で仕事をするようになってから、接客態度を含む顧客サービスのあり方と社会や経済の発展度合、基礎教育、職業訓練の重要性について改めて考えるようになった。私はかつて高い接客技術が求められる小売業に身を置いたことがあるので、この分野について一通り理解しているつもりである。そして過去、顧客第一の王道をネパール子ども病院の運営に応用した結果、開院以来の累積赤字が一年で一気に解消されたという経験も有している。
ところで、西アフリカの一部地域では、笑顔でお出迎え、顧客ニーズを読む、顧客の気持ちに寄り添うなどという、日本では顧客サービスの基本とも思える接客文化とは異なる場面に出くわす。サービスの質にばらつきが見られ、不誠実で、不適切なサービスに思えて閉口してしまうことも少なくない。良い接客を伴う上質のサービスは付加価値であり、客はそのサービスに価値を見出し、対価を払う。感激すれば心づけを添えるものだが、宿泊業、飲食業に加え、小売業でも何かがおかしい。客が客として大事に扱われていないような、客を定義する概念が別に存在しているかのように感じることさえある。他方、価値が低いと感じる商品やサービスに高額の値札がついていることがあるのだ。
その背景には、競争が極めて限定的な寡占状態にあることが一因として挙げられるが、多くの場合、経営者は自国民ではなく、国外にルーツを持つ外国人であることが多い。そして、決して例外がないわけではないが、彼らもまた良い接客がビジネスに付加価値をもたらすことを十分に理解していない、あるいは、長年培った商売の経験から「そこ」にコストをかける意義、費用対効果は低いと認識しているため、社員教育もいい加減で良いと判断している、そう推察できなくもない。
話をインドに戻すと、経済発展の帰結なのか、付加価値を積み上げた結果、経済が発展したのか、つまり鶏と卵の話になるが、教育への投資+システムや環境の整備→顧客サービス(=付加価値)の向上→利益の増加→ビジネスの拡充というセオリーは、最前線のサービス提供者の間でも理解されていることは明らかで、私が顧客であると認識される場面が日常的に存在した。

顧客サービスの一環として、公共の場における食の安全、顧客の権利などに対しても配慮がなされていることに驚いた。
私はデリー滞在中、世界遺産タージマハル廟で有名なアグラとの間の約2時間を(バスや車両による移動という選択肢もあったが交通渋滞を恐れ)特急列車で往復した。チケットの購入はアプリから行い、2等車(指定席)を選択した。チケットはもちろん切符ではなくQRコードだ。ものは試しと、予約の際に食事も(2時間の乗車中に果たしてどのようなものが出てくるのだろうかと思い)注文しておいた。なんとなんと、出てきた食事は値段の割に素晴らしいものだった。

車掌と兼任(?)と思しき配膳係が慣れた手つきでテキパキと乗客にサービスを提供していた。うーん、すでに日本では廃れたサービスがインドの電車内で当たり前のように提供されていることに感銘を受けた。
そして、食器のふたにはQRコードと製造年月日が記載されており、トレーサビリティ(調理からの履歴追跡が可能)も見かけ上は完ぺきだった。IT大国と呼ばれる所以である(七不思議5)。

そして何よりも驚いたのは、デリーへの帰路の車内で指定席券を持たずちゃっかり座席を占拠していた不届きな乗客(軍、あるいは警察関係者と思われる)に対し、車掌が厳しい態度で退去を命じている光景だった。秩序や公正さをあまり重視しない人々であると勝手に思い込んでいた自分を恥じた。もちろん、すべてがそうであるとは言えないが、限られた時間の中ではあっても、安価で安全で安心かつ快適な顧客サービスが提供されている状況を目の当たりにし圧倒された(七不思議6)。
大国インド、将来が恐しい。少し飛躍するが、すべてはあのラムチョップのお皿に凝縮している、そんな気がした。(続く)
理事長
大学卒業後、民間企業に就職。その後国連ボランティアとしてカンボジアや南アフリカの業務に従事、様々なフィールド経験を通じて国際協力業界へのキャリアチェンジを決意。大学院で国際開発学を学び、ミャンマーにおける人間開発プロジェクトに従事した後、1999年、AMDAグループ入職。ベネズエラ、インドへの緊急救援チームを率いた他、ネパール、アンゴラ、インドネシアなどで様々な事業運営に携わる。2002年、AMDA海外事業本部長就任。2007年、AMDA社会開発機構設立。理事長就任。趣味は旅行、山羊肉料理の堪能。岡山のお気に入りスポットは表町商店街とオランダ通り。神奈川県出身。

世界のことをもっと知りたい!
世界の貧困地域で暮らす人々の問題と、その解決に向けた私たちの取り組みをSNSとメールマガジンでも発信しています。まずは「関心をもつ」「知る」から始めてみませんか?!(過去のメールマガジンはこちらからご覧いただけます。)