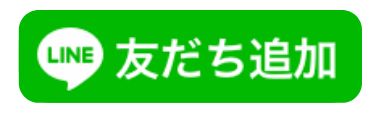うみがめ便り~20年の時を超えて、オノリンブの浜で思う③
前回の寄稿で、ニアス島における被災地復興支援プロジェクトがドリーム・プロジェクトだったとお伝えした。
しかし、プロジェクトを実施していた当時、とりわけ開始当初は困難の連続、ロジスティクスに関する障害が多く、行く末が大いに案じられた。プロジェクトが成功だったか否かは、プロジェクトが終了し、当初の活動計画が(軌道修正を含み)実施されたかどうか(プロセス評価)、当初掲げた目的が達成されたかどうか(有効性評価)、また達成された目的がその後も効果を維持できたかどうか(インパクト評価)によって測られることが多い。
留意点もある。活動が行われても外部要因(当事者が制御できない要素)の影響が大きいと目的は達成されない。また目的は達成できても、プロジェクト終了後の環境変化、想定外の資源不足等によって、効果が維持できない場合があるため、成功という二文字を獲得することは結構難しい。
いずれにしても「結果論」ではあるが、当プロジェクトの場合は、夢のような協力と住民参加が得られたこと、現地の文化を考慮したことにより成功に導かれた。以下、具体的に何点か挙げてみたい。
1.奇跡のロジスティックス~浜辺の大逆転
AMDAのプロジェクトは、当初目標に掲げられた簡易復興住宅をほぼ期間内に建設し終えることができた(様々な国際団体が住宅建設に取り組んだが、最も困難な地域の一つを担当したAMDAが、最も早く事業を終了した)。
陸送が困難だったため、ノルマンディー上陸作戦を彷彿させるかのように、建材を海岸から直接荷揚げするための手段(上陸用舟艇、フォークリフト、ショベルカー等)をWFPとUNHCRが提供してくれたことにより、もっとも困難なロジスティクスの課題が解決された。
さらに、(ニアス島における復興支援の新規定により、住宅を新たに建設する場合、浜辺から一定の距離を確保することが義務付けられたため)陸揚げされた建材を海岸線から数百メートル離れた住宅建設地まで運ぶ必要があったが、運搬用トラックがぬかるみの中、まさに液状化現象が起きたような浜辺の上を走行できるよう、ゴム製シートや蛇籠など、現場の状況に適した技術を駆使することによって走行を可能にした。これらはUNHCRの土木技術班の支援があってのことだった。
2.簡易復興住宅
今思うと、否、当時から感じていたが、あの屋根のデザインは秀逸だった。建設にやや手間はかかったものの、屋根が先端へ流れる途中で傾斜角度を緩和し、先端の約1メートルをひさしのように突き出したことにより、現地の伝統的家屋の風貌に似せたつくりとなった。
そのため、住民のアイデンティティと魂に響く住み家となり、また両隣が同じデザインの家に暮らすことになり、コミュニティに一体感をもたらした、と私は考える。もちろん、震災前に居住していた家屋は脆弱、貧弱だった可能性も高く、震災を機に頑丈な木造家屋を支援してもらえたことは幸運だと感じる家族も少なくなかったであろう。
家屋タイプは2種類あり、基礎の上にセメントの床を敷き、その上に材木の躯体を築く、従って家屋の壁面が地盤面に接するタイプと、基礎部分の上にコンクリートの基礎柱を立てた上で、木材の柱を置き高床式にするタイプの2種を用意し、建設地の環境や地盤を考慮した上で、住民の好みに合わせて選択してもらった。
プロジェクト側からは、害虫対策、湿気対策の点から高床式を勧めたが、前者のタイプを好む住民も少なくなかった。もう一つ重要な点は、付加価値としてブレース工法を採用した点である。躯体の縦横構造に金属をⅩ字型に取り付け、耐風、耐震性能を高めた。
たかが復興住宅とは言え、(私の記憶に間違いがなければ)UNHCRが雇用したオーストラリアの設計コンサルタントチームのおかげで、デザイン、耐震などの側面において、とても洗練された住宅の建設に携わることができたと、感謝の念を新たにしている。
3.住宅建設に係る住民参加
震災後の復興期、ニアス島では多くの国際NGOが復興住宅の建設に取り組んでいた。本邦NGOとしても力を尽くし、存在感を示すべき重要な機会であった。各団体の担当地域がどのように最終決定されたのかについては知る由もなかったが、現場での調整は容易ではなかったものと推察する。他方AMDAは、すでにUNHCRから任された地域が決まっていたため、このプロセスに費やす時間を省略でき、プロジェクト活動の戦略設計に傾注できた。我々が重視したのは、住民参加を住宅建設に取り込むことだった。団体の中には、大工チームを雇い、あるいは外注し、住宅が完成したら住民に引き渡す方法を採っていた。中にはセメント製のホローブロックを活用して、簡易復興住宅とは真逆の頑丈な家屋を建設する団体もあった。各団体がそれぞれの条件下で震災復興を定義し、その中で最良を求めた結果、地域(または村)によって良し悪し、優劣が生じたものの、ある意味いたし方ないと思われた。結果的に、高温多湿の場所ではセメントブロックによって建てられた住居よりも、風通しの良い木造家屋の方に軍配が上がり、AMDAが支援した住宅は特に居心地が良かったらしく、住民から大きく感謝された。
当時私は、木造の復興住宅は短くて5年、長くても10年を目途に建設するものだと考えた。しかし住民参加のセオリーを取り込めば、他人事ではなく自分事、授かりものではなく、オーナーシップを持ち続けることにより、上記期間は例えば10年~15年に伸びると考えた。問題はどの部分でどのように参加してもらうかである。月並みではあるが、木材、セメント、トタン屋根など、建設資材の保管、基礎工事に使う砂利や砂などの採取と運搬などに加え、建設工事にも住民参加を取り込んだ。
AMDAは運が良かった、そのひと言に尽きる。我々が担当した村には優秀な大工がいた。その名をカスマンと言う。そして海岸沿いの村だったため、家の建設に従事したことはないものの、木造の小舟の建造やメンテに携わった経験のある村人が複数いた。カスマン氏は、若かったが体格が良く、村人からも信頼されていた。彼の飲み込みは早く、すぐに他の即席大工に建設方法を伝授し、完工した復興住宅は倍々ゲームで増えていった。そしてその裏では、住民集会を開き、プロジェクト側と住民側の役割分担を理解してもらい、建設資材を調達、管理し、それらを各戸の玄関前まで運搬し、村人とともに考え、汗を流す仲間(邦人スタッフと現地スタッフ)がいた。
もちろん、すべてが順調に進んだわけではない。村に運んだ資材を密かに村外に運び出す不届き者がいて、それを指摘した邦人スタッフが刃物で脅され(最終的に警察が解決し)たり、また当初は、海岸に陸揚げされた木材をはじめとする大量の資材を建設現場まで運搬する術がなかったり、島内で調達できなかった資材を対岸のシボルガまで(沈没する可能性のあったフェリーに乗船して)調達したりと、様々な困難に直面する度に解決策が編み出され、課題は見事に克服されていった。ドリーム・プロジェクトと名付けた所以である。
さて、あれから20年が経過し、復興住宅は果たしてどう変わっていたか、うみがめは再びオノリンブの浜にたどりついた。しかしそこで玉手箱を開ける必要はなかった。なぜなら、うみがめは時の経過を感じさせない20年前の村を発見したからだ。(次号に続く)
理事長
大学卒業後、民間企業に就職。その後国連ボランティアとしてカンボジアや南アフリカの業務に従事、様々なフィールド経験を通じて国際協力業界へのキャリアチェンジを決意。大学院で国際開発学を学び、ミャンマーにおける人間開発プロジェクトに従事した後、1999年、AMDAグループ入職。ベネズエラ、インドへの緊急救援チームを率いた他、ネパール、アンゴラ、インドネシアなどで様々な事業運営に携わる。2002年、AMDA海外事業本部長就任。2007年、AMDA社会開発機構設立。理事長就任。趣味は旅行、山羊肉料理の堪能。岡山のお気に入りスポットは表町商店街とオランダ通り。神奈川県出身。

世界のことをもっと知りたい!
世界の貧困地域で暮らす人々の問題と、その解決に向けた私たちの取り組みをSNSとメールマガジンでも発信しています。まずは「関心をもつ」「知る」から始めてみませんか?!(過去のメールマガジンはこちらからご覧いただけます。)